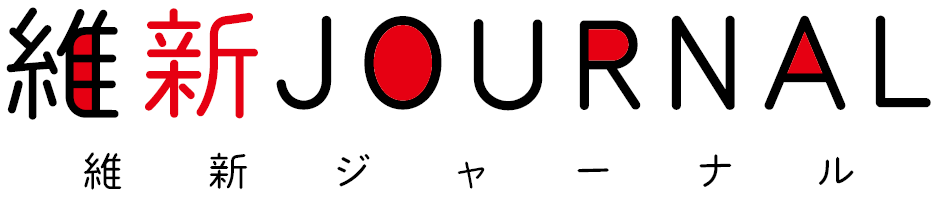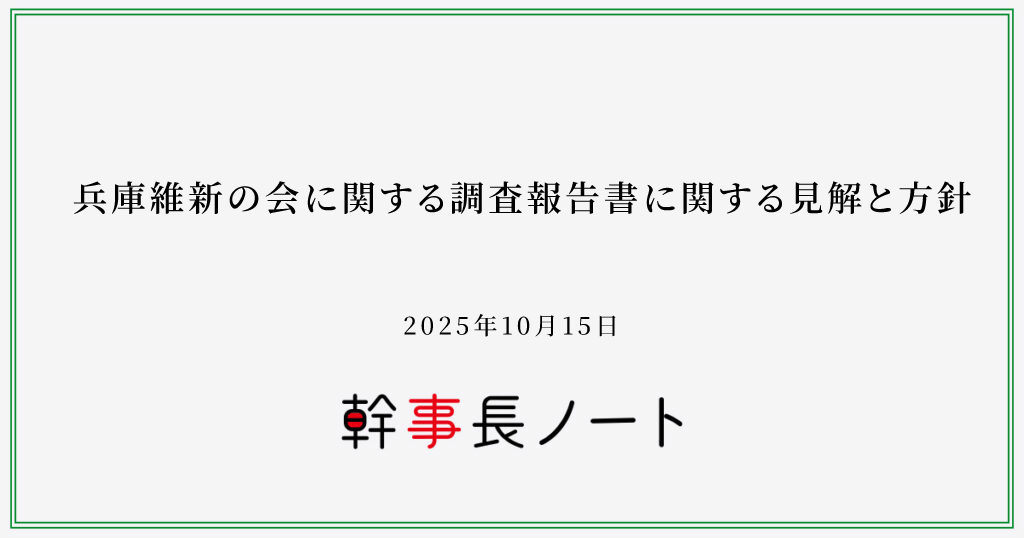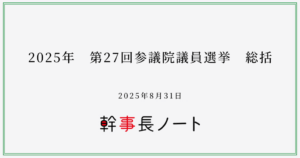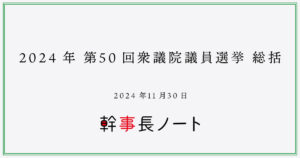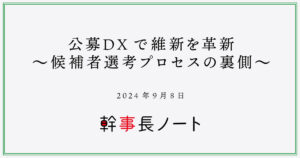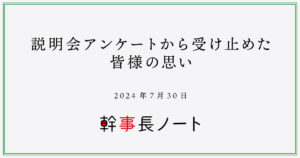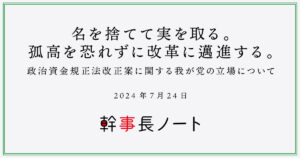令和7年10月15日
日本維新の会 幹事長 中司宏
令和7年6月4日、兵庫維新の会に関する調査委員会(東徹委員長、金城克典委員、坂井良和委員)が提出した調査報告書の一部が公開されたことに対し、調査方法や記載内容にたいする違和感から再調査を求める声、異議を唱える声が複数あった。しかしながら、本調査は第三者の弁護士も委員に名を連ねた独立した調査委員会が取りまとめたものであり、委員以外が調査報告書を修正できる性質のものではない。よって、党本部としては、下記の通り対応することとする。
- 兵庫維新の会所属議員(特に当事者である県議会議員)から、公開された総括部分の事実認定がどのようになされたかを判断するために調査報告書の全文を公開してほしいという要望があったことを踏まえ、下記の条件に合致する対象者のうち希望者のみに、日本維新の会幹事長、党本部事務局長、兵庫維新の会代表または幹事長の立会いのもと、閲覧を許可するものとする。ただし、その場での閲覧のみ許可し、複製複写は不可とする。
① 日本維新の会の常任役員及び非常任役員
② 日本維新の会の特別党員のうち、下記の条件に合致する者
A) 令和6年4月1日から現在までの間において、一時期でも兵庫維新の会の役員であった者
B) 令和6年4月1日から現在までの間において、一時期でも兵庫県議会議員団の役員であった者
C) 兵庫維新の会所属の衆議院議員、参議院議員
③ その他、特別な理由が認められ、日本維新の会幹事長が許可する者 - 公平性の観点から、再調査を求める声や異議を唱える声については、その趣旨や内容を含む代表的な主張をここに明記し、今後の判断材料とすることとする。
<調査報告書に対する代表的な主張の内容>
- 調査方法とヒアリング対象範囲の問題
- 本報告書の目的は、下記のように記載されている。
- 斎藤元彦兵庫県知事の告発文書に端を発して、①辞職勧告から知事不信任決議に賛成するという一連の活動(以下「本事案①」という)並びに②清水貴之氏の知事選への立候補及び選挙活動への関わり(以下「本事案②」という)について、
- 事実関係及び兵庫維新の会の意思決定の過程における対応やガバナンスの有効性を客観的かつ独立した立場から調査・検証すること、調査結果を踏まえた原因分析及び再発防止に向けた提言を行うこと
- 本事案①、本事案②について、当時の幹事長である藤田文武氏が党代表及び共同代表から正式な指示のもと党本部との連絡窓口としてサポートしていたことは周知の事実であるにも関わらず、ヒアリング対象に含まれなかった。
- 本報告書は組織のガバナンス欠如を結論づける内容であり、報告書本文には「党本部」の意向や「藤田文武」の名前が出てくる記述が複数あるにも関わらず、意図的にヒアリング対象から外されたのではないか。
- 本事案①②の当事者の1人であり、党本部側との受け渡し役として経緯を把握している藤田文武氏(当時の党幹事長)へのヒアリングを実施することなく事実認定を行っているのは重大な瑕疵である。
- 本報告書の目的は、下記のように記載されている。
- 公開方法の問題
- 全29ページに及ぶ報告書のうち、メディアに公開されたのは第3章「総括」が記載された17頁、18頁の2ページのみであった。
- 報告書の一部を抜粋して公開しているゆえに、結論や提言に至った事実認定部分との関係性が全くわからず、当事者は反論や検証をする材料もない状態である。
- 報告書内に個人名の記載があることへの配慮が必要という見解は一定理解できるが、そうであれば事実認定と結論の関係性が明記されるようにし、一部を抜粋して公開するのではなく、要約版をまとめ直して公開すべきである。
- 調査報告の内容の問題
- 総括には、「兵庫維新の会及び兵庫県議団は政党本来の目的である政策を立案し、これを実現するという役割とは異なり、党利党略、政争に明け暮れ、衆議院議員選挙、知事選挙に重点を置いた選挙互助会的な活動に熱心で、維新の目指す政策とは異なる決定が多く存在した」と、強い表現で断定されており、複数の当事者からは相当強い違和感が表明されている。しかしながら、本調査報告書には、その結論に至った事実認定が不明瞭であり、偏った印象論によって構成されている。
- 総括には、「兵庫県知事の信任・不信任や議会における百条委員会の問題は、そもそも維新県議会議員団が責任を持って決定すべき問題であった。いかに衆議院議員選挙と時期的に重なったとはいえ、衆議院議員支部長が自らの選挙に影響するとして、知事の辞職勧告や信任・不信任の問題にアドバイスの域を超え、その決定に参加し、声高に主導した。このことこそがガバナンスの欠如を生じた大きな原因であった。」と結論づけているが、衆議院議員支部長が「決定に参加」した事実はなく、またガバナンス欠如を生じさせる規約を超えた権限行使の事実も無い。調査報告書の事実認定は明確な誤りである。
- 本事案②について、知事選挙の対応の最終決定権限は、県総支部ではなく党本部にあるが、大型選挙は県総支部や県議団と一丸となって選挙戦を展開することから、党本部と県総支部所属議員との事前の意見交換が随時行われるのは当然のことである。令和6年9月28日(土)、オンライン併用にて藤田文武氏(当時の党幹事長)、片山大介氏(当時の兵庫維新の会代表)、兵庫県議会議員団所属議員が参加して、知事選対応の意見交換を目的とする会議が実施された。この会議では、知事選挙や衆議院議員選挙の想定日程、候補者として当時名前が上がっている方の状況を確認の上、我が党の対応について参加した県議会議員一人一人が意見とその理由を述べた。そこでは、①独自候補を擁立したいという意見、②斎藤知事を推薦したいという意見、③静観すべきという意見、④他候補へ相乗りすべきという意見など、所属議員から自由闊達に意見が出された。また、県議会議員の1人からは、清水貴之氏を口説いて擁立すべきではないかという個人名を挙げての意見があった。知事選挙の対応において、この会議は時期的にも内容的にも非常に重要なものであったが、調査報告書にはその記述が一切出てこない。
- 総括には、「幹事長が現場の党務すべてに責任を持つとしたうえで幹事長を地方議員から選挙で選任し、幹事長が政調会長・総務会長などの党の要職を指名することなど、地方議員の活動に期待する組織に変えることが検討されなければならない」と提言されている。現状の県総支部においては代表が選挙で選出され、幹事長は代表の指名であるが、党務を統括すべきトップ2名がそれぞれ別の選挙で選出されるという二重統治を生む提言であり、その趣旨には疑問が残る。
- 総括には「兵庫維新の会として、全員が目指すべき目標設定、すなわち政策を打ち立てることが必要である」との記載がある。そのうえで、統治機構改革、規制緩和、子育て支援策、行財政改革など具体的かつ詳細な提言が行われているが、これらの具体的な政策論やその優先順位こそ、地域事情などを踏まえて所属特別党員が責任を持って検討すべきものであり、第三者が独立性と中立性を持ってガバナンスの有効性を検証する本報告書の趣旨に合致しない。
以上